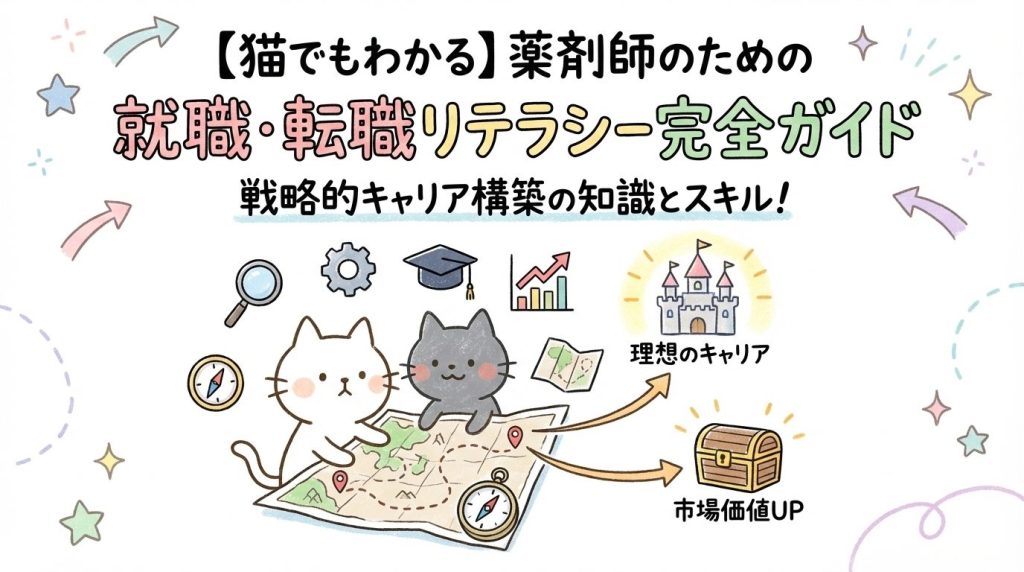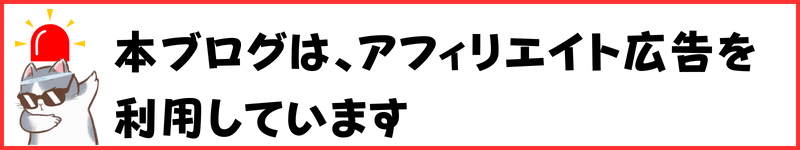薬剤師の就職・転職は単なる職場変更ではなく、キャリア形成の重要な一手です。しかし多くの薬剤師は転職リテラシーが低く、感情的な判断や表面的な条件だけで決断してしまいがち。本記事では薬剤師特有の就職・転職リテラシーを高め、戦略的なキャリア構築のための知識とスキルを解説します。
目次
薬剤師に就職・転職リテラシーが必要な理由

「年収が上がるから」「人間関係がきついから」「残業が多いから」—薬剤師の転職理由としてよく聞かれるフレーズです。このような理由で転職を繰り返すことは、長期的なキャリア形成において必ずしも最適な選択とは言えません。
私自身、薬剤師として15年のキャリアの中で様々な職場を経験してきました。多くの薬剤師が適切な就職・転職リテラシーを持たないまま、感情的な判断や待遇だけを見て仕事を選んでいる現状に危機感を覚えています。
マイナビ薬剤師の『薬剤師白書2023年度版』によると、薬剤師の34.6%が「給与条件」、31.7%が「人間関係」を理由に退職を考え始めていますが、長期的なキャリアビジョンに基づいた転職は少数派です。
薬剤師って「給料が良い」「休みが取れる」みたいな表面的な条件だけで転職先を選んじゃう人が多いんだよね。でも本当は「就職・転職リテラシー」が大切なんだ。

クロ

シロ
就職・転職リテラシーって何?難しそう…
今の働き方、60秒で診断しませんか?
調剤・病院・企業など 5万件超 の薬剤師求人を保有。
希望条件を入力するだけで、あなたに合う求人を提案します。
- 最短60秒で完了する簡単登録
- 条件にマッチした厳選求人をご紹介
- 非公開求人も多数保有
◉ 最適な求人をチェックする
就職・転職リテラシーとは何か?一般職との比較

就職・転職リテラシーの定義
就職・転職リテラシーとは、「仕事選びや転職に関する適切な知識と判断力」を指します。具体的には以下の要素が含まれます:
- 自己分析力: 自分のスキル、強み、価値観を客観的に把握する能力
- 業界理解力: 業界の現状と将来性を分析する能力
- 情報収集力: 転職市場や企業の実態について正確な情報を集める能力
- 交渉力: 自分の希望条件を適切に主張し、調整する能力
- 長期的視点: 目先の条件だけでなく、キャリア全体を見据える視点
一般職と薬剤師の転職リテラシーの違い
一般職と専門職である薬剤師では、転職リテラシーにおいて以下のような違いがあります:
| 比較項目 | 一般職 | 薬剤師 | 薬剤師の特徴 |
|---|---|---|---|
| 転職市場の透明性 | 比較的高い | 限定的 | 業界内の情報が閉鎖的 |
| スキルの可視化 | わかりやすい (資格・経験など) | わかりにくい (臨床経験・専門性) | 専門性の証明が困難 |
| キャリアパスの多様性 | 非常に多様 | 限定的だが徐々に拡大 | 専門性を活かした多様化が進行中 |
| 転職頻度の許容度 | 業界による | 比較的低い | 薬歴の継続性が重視される |
| 転職市場の競争率 | 職種による | 地域差が大きい | 都市部は競争が激しい |
これは専門職のキャリア観や転職市場の特性によるものですが、適切な転職リテラシーを持つことで、薬剤師もより戦略的なキャリア選択が可能になります。
一般職から学ぶべき転職リテラシー
一般職、特にIT業界や営業職など転職が活発な業界のプロフェッショナルから薬剤師が学ぶべき点は多くあります:
- スキルの可視化と言語化
- 一般職:具体的な実績や数値で自分の価値を示す
- 薬剤師への応用:担当した処方箋枚数だけでなく、介入した症例数や改善した業務プロセスなど
- プロジェクト型思考
- 一般職:一つの会社にこだわらず、「挑戦したいプロジェクト」で選ぶ
- 薬剤師への応用:特定の疾患領域のスキルアップや新たな薬局モデルへの参画など
- 複数収入源の確保
- 一般職:副業・複業の一般化
- 薬剤師への応用:非常勤勤務の組み合わせや、セミナー講師など専門性を活かした活動
一般職だと「この会社で3年でこんなスキルを身につけて、次はこの会社でこの経験を積む」みたいに計画的に転職する人が増えてるんだよね。薬剤師もそういう視点が必要なんだ!

クロ

シロ
なるほど!薬剤師って「ずっと同じ職場」か「何となく転職」の二択だったけど、もっと戦略的に考えられるんだね。
薬剤師の市場価値を測る8つの質問

薬剤師として自分の市場価値を客観的に把握することは、就職・転職リテラシーの第一歩です。以下の質問に答えることで、自分の現在地が見えてきます。
1. どのようなスキル・知識が他の職場でも通用するか?
単なる調剤業務だけでなく、以下のようなスキルは汎用性が高いです:
- 特定疾患(がん・糖尿病・感染症など)の専門知識
- サプライチェーン管理能力
- 医薬品情報管理・評価能力
- 多職種連携・コミュニケーションスキル
2. そのスキルの「消費期限」はいつまでか?
薬学の知識は日々更新されています。「旧態依然とした知識」と「最新知識」を区別し、継続的な学習が必要です。
例えば:
- 電子お薬手帳やオンライン服薬指導など新しいデジタル技術への対応
- 最新のガイドラインや治療法の知識
- 医療制度改革への理解
3. 他の職場でも通用する「レアな経験」がどれだけあるか?
以下のような経験は市場価値が高い傾向にあります:
- 在宅医療の経験
- 緩和ケア・終末期医療の経験
- 特殊な製剤技術(抗がん剤調製など)
- 医療安全管理のシステム構築経験
- 薬局管理者・開設者としての経験
4. その経験は、世の中からどれだけニーズがあるか?
厚生労働省の「患者のための薬局ビジョン」や調剤報酬改定の動向を踏まえると、以下の分野のニーズが高まっています:
- 健康サポート薬局に関するスキル
- ポリファーマシー対策のノウハウ
- 地域連携・多職種連携の経験
- 医薬品適正使用のための臨床判断能力
5. 職場に、環境を変えても力を貸してくれる人物がどれだけいるか?
上司や同僚との関係性も重要な資産です:
- メンターとなる先輩薬剤師
- 業務推薦を書いてくれる管理薬剤師
- 転職先を紹介してくれる同業者
6. 社外に、自分のために力を貸してくれる人物がどれだけいるか?
業界内の人脈は長期的な市場価値を高めます:
- 学会や勉強会での人脈
- 前職の同僚・上司とのネットワーク
- SNSなどでの専門家コミュニティ
7. 薬剤師業界の今後の「成長性」はどうか?
薬剤師業界全体の動向を見極めることも重要です:
- 調剤業務の機械化・自動化の進展
- 対人業務へのシフト
- 薬局再編の動き(健康サポート薬局、地域連携薬局など)
8. 今後、どれだけ「自分の市場価値」を高めることができるか?
現在の職場が以下の機会を提供しているかを考えましょう:
- 専門性を高める学習機会
- 新たな役割・業務への挑戦機会
- 資格取得のサポート
この8つの質問に答えられると、自分の薬剤師としての市場価値がはっきり見えてくるんだよね。特に若いうち(30代前半まで)は「専門性」を、それ以降は「経験」を重視すべきなんだ。

クロ

シロ
へぇ〜。今まで「年収」とか「休日数」しか見てなかったけど、もっと大事なことがあったんだね!
ファルマスタッフで転職相談満足度 96.5%
就業先を直接訪問したコンサルタントが残業・雰囲気まで共有。
東証プライム上場グループ運営で安心です。
- 現場を知り尽くしたプロによるサポート
- 書類では分からない職場の空気感も把握
- 24時間いつでも相談可能なシステム
◉ ファルマスタッフに登録する
「これからの仕事と転職のルール」を理解する

働き方の大きな変化
一般職では既に「終身雇用」から「ジョブ型雇用」「プロジェクト型雇用」へのシフトが進んでいます。薬剤師業界でも遅ればせながらこの変化が始まっています。
リクルートワークス研究所の調査によると、2023年時点で日本の労働人口の約23%がジョブ型雇用で働いていますが、医療系専門職では8%程度にとどまっています。この差が「転職リテラシー」の差とも言えるでしょう。
「いつでも転職できる状態」を維持する重要性
これからの時代、「一つの職場に依存する」リスクは非常に高くなっています。特に薬剤師業界では、テクノロジーの進化や制度改革により、求められるスキルセットが急速に変化しています。
「いつでも転職できる状態」を維持するためには:
- 常に市場価値を高める行動をとる
- 専門性の構築・維持
- 新しい業務への挑戦
- 自己啓発・学習
- 業界の動向をチェックし続ける
- 調剤報酬改定の内容理解
- 薬局機能の再編動向
- テクノロジーの進化
- 人脈を構築・維持する
- 学会・勉強会への参加
- SNSなどでの専門的発信
- 前職の同僚とのつながり維持
「会社にしがみつく」リスク
多くの薬剤師が「安定」を求めて大手チェーンや大学病院などの「ブランド」にしがみつく傾向がありますが、このアプローチには以下のようなリスクが伴います:
- スキルの陳腐化
- 同じ環境での限られた経験
- 新しい知識・技術へのアップデート機会の不足
- 交渉力の低下
- 「この会社しか選択肢がない」という依存関係
- 給与・待遇改善の要求が困難に
- 突然のリストラや環境変化への脆弱性
- 薬局再編や買収による環境変化
- 業務の自動化・効率化による人員削減
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、転職経験のある薬剤師の方が、同一組織に10年以上勤務している薬剤師と比較して、平均年収が5〜8%高い傾向にあります。これは交渉力の差によるものと考えられます。
今後重要になる薬剤師の役割
労働市場で価値を維持するためには、将来のニーズを先読みする必要があります。薬剤師に関しては、以下の領域が重要性を増すと予測されています:
- 患者中心のケアコーディネーション
- ポリファーマシー対策
- 薬物治療の一元管理
- 多職種連携のハブ機能
- 予防医療・健康管理の専門家
- 健康サポート機能
- 生活習慣病予防の指導
- セルフメディケーション支援
- デジタルヘルス・医療ITの活用
- 電子お薬手帳の活用
- オンライン服薬指導
- 医療ビッグデータの分析
- 特定領域の専門家
- がん、感染症、精神科など特定疾患
- 在宅医療
- 緩和ケア
これからの時代は「会社があなたを守る」時代じゃなくて「自分の市場価値で自分を守る」時代なんだよね。薬剤師も例外じゃないんだ。

クロ

シロ
そうか、だから「いつでも転職できる状態」を維持することが大事なんだね。でも具体的にはどうすればいいの?
転職エージェントの効果的な活用法

転職エージェントのビジネスモデルを理解する
転職エージェントのビジネスモデルは「企業から成功報酬を得る」ことです。一般的に年収の30〜35%程度が相場です。このビジネスモデルを理解した上で付き合うことが重要です。
エージェント選びのポイント
すべての転職エージェントが同じではありません。薬剤師の場合、以下のポイントで選ぶことをお勧めします:
- 業界専門性
- 薬剤師専門のエージェントか
- 薬剤師業界の動向に詳しいか
- コンサルティング力
- 単なる求人紹介ではなく、キャリア相談に乗ってくれるか
- 長期的なキャリアプランを一緒に考えてくれるか
- 求人の質と量
- 非公開求人の数と質
- 大手チェーンから個人薬局まで幅広い選択肢
- 信頼性と実績
- 「職業紹介優良事業者認定」の取得
- 口コミや評判
薬剤師専門の転職エージェントとしては、「マイナビ薬剤師」「ファルマスタッフ」などが職業紹介優良事業者認定を取得しており、求人数・評判ともに安定しています。
複数のエージェントを利用する理由
一つのエージェントだけでなく、複数のエージェントを利用することをお勧めします:
- より多くの求人情報にアクセスできる
- エージェントによって扱う求人が異なる
- 非公開求人の幅が広がる
- 市場価値の正確な把握
- 複数のエージェントからの評価で自分の市場価値を把握
- 条件交渉の参考になる
- サービス品質の比較
- 担当者の質やサポート内容の比較
- より自分に合ったエージェントを見つけられる
一般的に、主要なエージェント2〜3社に登録しておくことで、選択肢を広げることができます。
エージェントとの効果的な付き合い方
- 自分のキャリアビジョンを明確に伝える
- 単なる条件だけでなく、長期的な目標も共有
- 「何を学びたいか」「どんな環境で働きたいか」を伝える
- 情報を鵜呑みにしない
- 提案された求人について自分でも調査する
- 「良い条件の求人」の裏にある事情を考える
- 定期的なコミュニケーション
- 1〜2ヶ月に一度は状況確認
- 市場動向について情報収集
- 転職する/しないの決断は自分で行う
- エージェントのアドバイスは参考にするが、最終判断は自分で
- 「今は転職しない」という選択肢も持つ
転職エージェントは便利だけど、彼らのビジネスモデルをわかった上で付き合うことが大事なんだよね。「紹介して入社してもらう」ことで報酬を得るから、時々急かされることもあるんだ。

クロ

シロ
なるほど!複数のエージェントを比較して、自分に合った担当者を見つけるのがコツなんだね。でも転職先をどう見極めればいいの?
転職先の徹底的な調査方法

表面的な情報だけで判断しない
多くの薬剤師が「給与」「休日数」「残業時間」といった表面的な条件だけで転職先を選んでしまいますが、より深い調査が必要です。
公開情報から読み取れること
以下の公開情報から転職先の実態を把握することができます:
- 薬局機能情報提供制度(薬局機能情報サイト)
- 各都道府県が運営する公式サイト
- 薬剤師数、開局時間、対応サービスなどの基本情報
- 企業の財務情報
- 上場企業の場合は有価証券報告書
- 非上場企業でも法人登記簿謄本など
- SNSでの評判や投稿
- 従業員のSNS投稿
- 口コミサイトの評価(転職会議など)
- 求人情報の出現頻度
- 同じ求人が頻繁に出ているのは要注意
- 過去の求人と給与・条件の比較
面接・見学時に確認すべきポイント
面接や職場見学の機会は、転職先を見極める重要な機会です:
- 現場の雰囲気
- スタッフ同士のコミュニケーション
- 患者対応の様子
- 清潔感や整理整頓の状況
- 具体的な質問
- 「直近1年間の離職率は?」
- 「有給休暇の取得率は?」
- 「研修制度や学習支援はどうなっていますか?」
- 「昇給・評価制度はどのようになっていますか?」
- 管理者・先輩薬剤師との会話
- 在籍年数
- キャリアパス
- 仕事の満足度
「隠された情報」の調査方法
表に出ていない情報を把握するための方法:
- 同業者ネットワークの活用
- 元従業員や取引先からの情報収集
- 業界の噂話も鵵呑みにせず参考程度に
- 近隣医療機関の評判
- 近隣医療機関との連携状況
- 処方元の医師からの評価
- 患者からの口コミ
- Googleマップなどの口コミ
- 地域での評判
- 第三者評価
- 各種表彰・認定の有無
これらの情報を総合的に判断することで、表面的な条件だけでは見えてこない職場の実態が見えてきます。
薬剤師のためのレッドフラッグ(警戒サイン)
以下のような兆候が見られる職場は注意が必要です:
- 高すぎる給与提示
- 市場相場より明らかに高い給与
- 「〜まで可能」という表記
- 極端な離職率
- 短期間での薬剤師の入れ替わり
- 同じ求人の繰り返し掲載
- 曖昧な回答
- 勤務条件についての具体的な説明がない
- 「忙しい時期は」という言葉が多い
- 設備・環境の不備
- 古すぎる調剤システム
- 狭い休憩スペース
- 医薬品の管理状態
転職先を選ぶときは、給料や休みだけじゃなくて「将来そこで何が学べるか」「キャリアにどう役立つか」を考えることも大事なんだよ。人間関係や職場の雰囲気も見逃せないポイントだよね。

クロ

シロ
なるほど!面接では質問をたくさんして、見学もしっかりして、本当にそこで働きたいか確かめることが大事なんだね。でも最終的にはどう決めればいいの?
これからの時代の薬剤師キャリアデザイン

従来型キャリアパスからの脱却
従来の薬剤師キャリアは「一つの職場で昇進・昇給を目指す」モデルが主流でしたが、これからは「自分の市場価値を高めながら最適な場所を選ぶ」モデルへの転換が求められています。
10年単位のキャリアデザイン
キャリアデザインは短期的ではなく、10年単位で考えることが重要です:
- 20代〜30代前半:専門性構築期
- 基礎スキルの徹底的な習得
- 特定領域の専門性確立
- 資格取得
- 30代後半〜40代:経験蓄積期
- 多様な経験の獲得
- マネジメントスキルの開発
- ネットワーク構築
- 40代後半〜:専門性活用期
- 培った専門性の活用
- 後進の育成
- ワークライフバランスの最適化
クロスボーダー型キャリア
一つの領域にとどまらず、関連領域を横断するキャリア構築も選択肢となります:
- 薬局×病院
- 薬局での経験を活かして病院へ
- 病院での臨床経験を薬局で活用
- 臨床×企業
- 臨床経験を活かして製薬企業へ
- MRから薬局薬剤師へ
- 実務×教育
- 現場経験を活かして教育機関へ
- 研修講師や大学講師との兼業
ポートフォリオワーク
一つの職場に依存せず、複数の収入源を持つ働き方も増えています:
- 複数の薬局でのパート勤務
- リスク分散
- 多様な経験の獲得
- 本業+副業
- 薬剤師としての勤務+セミナー講師
- 調剤業務+医薬品情報提供業務
- フリーランス薬剤師
- 複数の医療機関と契約
- プロジェクトベースの仕事
キャリア形成における「選択と集中」
すべての分野でスキルを高めることは現実的ではありません。以下のような「選択と集中」が重要です:
- 得意分野の明確化
- 自分の強みを把握
- 市場ニーズとの一致点を探る
- 不得意分野の委託・連携
- すべてを自分でやろうとしない
- チームや組織の力を活用
- 定期的な棚卸し
- 3年ごとに自分のスキルと市場ニーズを再評価
- 必要に応じて注力分野を調整
薬剤師のキャリアも「一つの会社で一生」じゃなくて、いろんな経験を積んで市場価値を高めていく時代なんだね。年代によって目指すものも変わってくるよ。

クロ

シロ
へー!「20代は専門性」「30〜40代は経験」「40代以降は専門性の活用」って感じなんだね。私も将来を見据えて今から準備しないと!
初めての転職でも安心の No.1 実績
非公開求人の紹介・面接同行も完全無料。
まずは希望条件だけ伝えてみませんか?
- 初めての転職に選ばれるNo.1
- 20代・30代に強い薬剤師転職サイトNo.1
- ハイクラス転職に強い薬剤師転職サイトNo.1
※日本マーケティングリサーチ機構調べ(2021年11月)
\無料キャリア相談を予約/◉ 今すぐファルマスタッフに登録
よくある質問(FAQ)
Q1: 薬剤師が転職回数が多いとマイナスになりますか?
A1: 単純な転職回数よりも「転職の質」が重要です。キャリアアップや専門性向上のための転職は、むしろポジティブに評価されることが増えています。ただし、1年未満の短期間での頻繁な転職は「定着性の低さ」と判断されるリスクがあります。厚生労働省の調査では、薬剤師の平均在職期間は4.2年であり、3〜5年程度で次のステップに進むケースが多くなっています。
Q2: エージェントを通さない直接応募と、エージェント経由ではどちらが有利ですか?
A2: 状況によります。エージェント経由のメリットは「非公開求人へのアクセス」「条件交渉のサポート」「選考対策」などがあります。直接応募のメリットは「自分のペースで進められる」「企業への熱意を直接伝えられる」点です。大手チェーンや病院は直接応募も可能ですが、中小の薬局や非公開求人はエージェント経由の方が選択肢が広がります。両方を併用するのが最も効果的です。
Q3: 年収アップだけを目的とした転職は避けるべきですか?
A3: 単純な年収アップだけを目的とした転職は長期的には推奨できません。なぜなら:
- 高給与の裏には高負荷や特殊条件がある場合が多い
- スキルアップがない環境では将来の市場価値が下がる可能性がある
- 給与以外の要素(成長機会、ワークライフバランス、職場環境)も幸福度に大きく影響する
年収アップを目指すなら、「スキルアップを通じた市場価値向上→それに見合った報酬」というプロセスを意識すべきです。
Q4: 専門・認定薬剤師の資格は転職に有利ですか?
A4: 多くの場合、専門・認定薬剤師の資格は転職市場での価値を高めます。特に、がん専門薬剤師や感染症専門薬剤師などは需要が高い傾向にあります。ただし、資格を活かせる職場を選ぶことが重要です。例えば、地域密着型の一般薬局ではがん専門薬剤師の知識を十分に活かせない場合もあります。資格取得は「どのような職場で活かしたいか」という将来ビジョンと合わせて検討すべきです。
Q5: 薬局と病院、どちらでキャリアをスタートさせるべきですか?
A5: どちらが「良い」というわけではなく、自分のキャリアビジョンによります:
薬局スタートのメリット:
- より幅広い薬剤の知識を習得できる
- 患者コミュニケーション能力が向上しやすい
- マネジメント経験を得やすい
病院スタートのメリット:
- 臨床的な専門知識を深められる
- チーム医療の経験を積める
- 特定疾患の専門性を高めやすい
理想的には、キャリアの中でどちらも経験することで、より市場価値の高い薬剤師になれます。厚生労働省の調査では、両方の経験を持つ薬剤師の方が平均年収が約8%高いというデータもあります。
まとめ:薬剤師のための就職・転職リテラシーを高めるために

薬剤師のための就職・転職リテラシーを高めることは、これからの時代に自分のキャリアを守り、発展させるために不可欠です。この記事でお伝えしたポイントをまとめます:
- 就職・転職リテラシーの重要性
- 表面的な条件だけでなく、長期的キャリア形成の視点で判断する
- 一般職の転職リテラシーから学ぶべき点が多い
- 市場価値を高める意識
- 若いうちは「専門性」、それ以降は「経験」に注力
- 常に「いつでも転職できる状態」を維持する
- 転職エージェントの戦略的活用
- ビジネスモデルを理解した上で複数のエージェントを活用
- 情報を鵜呑みにせず、自分でも調査する
- 転職先の徹底的な調査
- 表面的な条件だけでなく、職場環境や将来性も評価
- 「隠された情報」の収集方法を知る
- 将来を見据えたキャリアデザイン
- 10年単位の長期的視点
- クロスボーダー型キャリアやポートフォリオワークの検討
私自身、15年の薬剤師キャリアの中で様々な選択を経験し、転職リテラシーの重要性を痛感してきました。「給料が良いから」「通勤が楽だから」といった表面的な理由ではなく、「自分の市場価値を高められるか」「将来のキャリアにどう活きるか」という視点で仕事を選ぶことが、長期的な満足につながります。
結局大事なのは「自分の市場価値を高め、いつでも転職できる状態を維持すること」なんだね。そうすれば会社にしがみつく必要もなくなるし、自分らしいキャリアが築けるよ。

クロ

シロ
なるほど!転職するしないに関わらず、常に自分の価値を高めておくことが大切なんだね。今日から私も市場価値を意識して働いてみるよ!
薬剤師としてのキャリアデザインは、自分自身で主体的に描いていくものです。適切な就職・転職リテラシーを身につけ、変化の激しい医療環境の中でも、自分らしく輝き続けるキャリアを築いていきましょう。