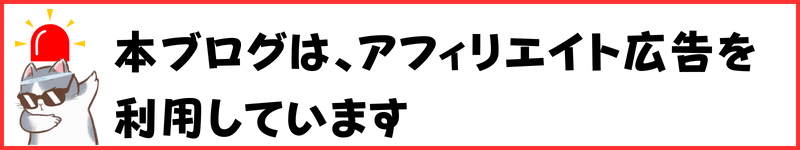薬学部を卒業したけど「情熱的にやりたいこと」が見つからない…そんな悩みを抱える薬剤師は想像以上に多いものです。本記事では「やりたいこと」の神話を解体し、自分らしく薬剤師として働き続けるための考え方と実践的アドバイスをお届けします。薬剤師15年のキャリアから得た気づきを共有します。
目次
「やりたいこと」がない罪悪感に苦しむ薬剤師たち

「本当にやりたいことがないのに、このまま薬剤師を続けていいのだろうか…」
このような悩みを抱える薬剤師は、思いのほか多いものです。私自身も薬剤師として15年のキャリアの中で、何度もこの自問自答を繰り返してきました。特に転職活動をする際に「御社で何を実現したいですか?」という質問にどう答えていいか悩んだ記憶があります。
薬学部を選んだ理由も「化学が好きだった」「安定した職業だから」「親や先生に勧められて」という方も少なくありません。「幼い頃から人の命を救いたくて…」というドラマチックな志望動機を持つ人ばかりではないのが現実です。
しかし、「やりたいこと」がないことに罪悪感を抱く必要はありません。その理由を詳しく見ていきましょう。
薬剤師って「やりたいこと」を聞かれるとなんだか答えにくいよね。私は患者さんを助けたいって言ってるけど、本当はなんとなく流れで薬剤師になっただけだし…

クロ

シロ
えっ、そうなの?私もなんとなく安定してそうだなって思って選んだけど、周りはみんな立派な志があるみたいだから言えなかったよ…
今の働き方、60秒で診断しませんか?
調剤・病院・企業など 5万件超 の薬剤師求人を保有。
希望条件を入力するだけで、あなたに合う求人を提案します。
- 最短60秒で完了する簡単登録
- 条件にマッチした厳選求人をご紹介
- 非公開求人も多数保有
◉ 最適な求人をチェックする
「やりたいこと」神話の解体:to do型とbeing型の人間

多くの人が「やりたいこと」がないことに悩みますが、実はこれは現代社会が生み出した「神話」かもしれません。キャリア理論の観点から見ると、人間のキャリア志向は大きく2つのタイプに分けることができます。
| 比較項目 | to do型(コト重視) | being型(状態重視) | 特徴(being型) |
|---|---|---|---|
| 仕事の捉え方 | 達成したい目標がある | 自分らしく働ける環境が大事 | 無理をしない自然体の働き方 |
| モチベーション源 | 具体的な目標達成 | 価値観との一致・心地よさ | 強制ではなく選択の自由がある |
| キャリア選択基準 | 目標達成に役立つか | 自分の価値観に合うか | 自己一致感が高い環境を選ぶ |
| 仕事の満足度 | 目標達成できるか | 自分らしく働けるか | 「嘘」をつかなくて済む環境 |
| 人口割合 | 約10〜15% | 約85〜90% | 実は多数派である |
to do型(コト重視)の特徴
to do型の人は「何をするか」が重要です。明確な目標や夢があり、それに向かって突き進む傾向があります。例えば「がん専門薬剤師になる」「在宅医療の分野で起業する」など、具体的なビジョンを持っています。
キャリアカウンセリングの専門家によると、このタイプは全体の10〜15%程度と言われています。社会的に目立つ「成功者」には多いタイプですが、実は少数派なのです。
being型(状態重視)の特徴
being型の人は「どんな状態でありたいか」を重視します。「やりがいのある環境で働きたい」「良好な人間関係の中で過ごしたい」「仕事と家庭のバランスを保ちたい」など、自分の価値観や心地よさを優先します。
最近の心理学研究では、実は人口の85〜90%がこのタイプだと言われています。つまり、「やりたいこと」が明確でないのは、むしろ普通のことなのです。
being型の人が仕事を続ける上で最も重要なこと
being型の人が職業に満足して長く続けるために最も重要なのは、「仕事でつく嘘を最小化すること」です。具体的には:
- 自分の価値観と矛盾する行動を強いられない
- 「本当はこう思うけど、会社のために違うことを言う」という状況が少ない
- 自分らしさを抑圧せずに働ける環境
心理学者のカール・ロジャースは、この「自己一致」の状態が精神的健康の重要な要素だと指摘しています。
薬剤師業界の特性と「やりたいこと」の関係

薬剤師業界には、「やりたいこと」と職業選択の関係において特徴的な点があります。
薬剤師の職業選択理由の実態
マイナビ薬剤師の『薬剤師白書2023年度版』のデータによると、薬剤師を志した理由は多様です:
- 「安定した職業だから」: 42.3%
- 「化学や生物が好きだった」: 38.7%
- 「医療に貢献したかった」: 35.9%
- 「家族や先生の勧め」: 23.1%
- 「明確な将来ビジョンがあった」: 18.6%
明確な「やりたいこと」があって選んだ人よりも、安定性や科目の得意さなど現実的な理由で選んだ人の方が多いのが現実です。
薬剤師のやりがいの源泉
同調査では、薬剤師がやりがいを感じる瞬間として以下が挙げられています:
- 「患者に感謝されたとき」: 69.4%
- 「自身のスキルアップ・成長を感じるとき」: 39.5%
- 「チーム・職場全体で仕事に取り組んでいるとき」: 28.9%
- 「困難な仕事をやり遂げたとき」: 28.9%
これらは「大きな目標達成」よりも、日常の小さな瞬間や人間関係から得られる充実感が中心です。つまり、being型の人が満足できる要素が多いのが薬剤師という職業の特徴とも言えます。
ファルマスタッフで転職相談満足度 96.5%
就業先を直接訪問したコンサルタントが残業・雰囲気まで共有。
東証プライム上場グループ運営で安心です。
- 現場を知り尽くしたプロによるサポート
- 書類では分からない職場の空気感も把握
- 24時間いつでも相談可能なシステム
◉ ファルマスタッフに登録する
「やりたいこと」がなくても薬剤師として働く価値

「やりたいこと」がなくても、薬剤師として働く価値は十分にあります。その理由を考えてみましょう。
社会的意義の再認識
薬剤師の仕事は、患者の健康と安全を守る重要な役割を担っています。WHO(世界保健機関)が発表した「患者安全のグローバルアクション」では、薬物治療の安全性向上において薬剤師の役割が不可欠とされています。
日々の業務が直接人の命や健康に関わるという社会的意義は、「やりたいこと」を超えた価値があります。
職業としての実利的メリット
薬剤師は実利的なメリットも豊富です:
- 安定した雇用: 医療系国家資格の強み
- ワークライフバランス: 特にパート勤務などの柔軟な働き方
- 多様なキャリアパス: 病院、薬局、企業、行政など
- 収入の安定: 平均年収500〜600万円(2024年度データ)
「やりたいこと」が見つからない間も、これらの実利的メリットは人生における土台を提供してくれます。
「職業≠アイデンティティ」という視点
アメリカの社会学者デイビッド・グレーバーは著書『ブルシット・ジョブ』で、現代の「仕事がアイデンティティの中心でなければならない」という考え方に疑問を投げかけています。
仕事は収入を得るための手段であり、本当の自己実現はプライベートの時間で追求するという選択肢も十分にあります。薬剤師として働きながら、趣味や家族との時間、地域活動などで充実した人生を送ることは可能です。
「やりたいこと」を見つけるのではなく「続けられること」を探す

「やりたいこと」を探し続けるよりも、「続けられること」を見つけるアプローチが効果的な場合があります。
小さな「好き」の発見法
心理学者ミハイ・チクセントミハイの「フロー理論」によれば、人は夢中になれる活動で幸福感を得られます。薬剤師業務の中から小さな「好き」を見つける方法を考えましょう:
- 業務の棚卸しをする:
- 1週間の業務を15分単位で記録してみる
- それぞれの業務で「エネルギーが湧く/下がる」を評価
- 得意分野に注目する:
- 自分が周囲からよく質問される分野は何か
- 努力せずに自然と身についた知識・スキルは何か
- 嫌いではない業務を増やす:
- 好きな業務が見つからなくても、嫌いな業務を減らす
- 無意識に避けている業務に向き合い、改善方法を見つける
「やりたいこと」は後からついてくることも
キャリア研究者のカル・ニューポートは著書『DEEP WORK』で「パッション仮説」を批判し、多くの人の情熱は「あとから発見される」と論じています。
具体的には:
- スキルを磨き、専門性を高める
- 徐々に自律性が増していく
- 認められ、評価される経験を積む
- そこで初めて「情熱」が生まれる
薬剤師としても、最初は漠然と働き始め、徐々に専門性を高めることで、後から「やりたいこと」が見つかるケースは珍しくありません。
クロ:実は「やりたいこと」って後からついてくることも多いんだよ。まずは「続けられること」「耐えられること」から始めて、少しずつ専門性を高めていくと、いつの間にか「好き」に変わってたりするんだ。
シロ:そうなんだ!「好き」を無理に探さなくてもいいんだね。私も「嫌い」を減らす方向で考えてみようかな。
自分を守りながら薬剤師として働く実践的戦略

being型の人が「自分の嘘」を最小化しながら薬剤師として働くための実践的な戦略を考えてみましょう。
市場価値を高める
薬剤師としての市場価値を高めることは、選択肢と自由度を広げる最も効果的な方法です:
- 専門性の構築:
- 特定疾患(糖尿病、がん、感染症など)の専門知識
- 認定・専門薬剤師の資格取得
- 学会発表や論文執筆
- 横断的スキルの習得:
- コミュニケーション能力
- データ分析スキル
- マネジメント能力
- ネットワークの構築:
- 学会や業界イベントへの参加
- SNSなどでの情報発信
- 多職種連携の積極的な実践
「NO」が言える環境を選ぶ
自分の価値観と合わない業務や環境に「NO」が言える状況を作ることが重要です:
- 職場選びの基準を明確にする:
- 同僚の離職率
- 有給休暇取得率
- 残業時間の実態
- ハラスメント対策の有無
- 境界線を設定する勇気:
- 過剰な業務要求への断り方の練習
- 自分の限界を認識し伝える
- 協力的な同僚・上司との関係構築
- 複数の収入源を持つ:
- パート・非常勤の組み合わせ
- 副業・複業の可能性
- 経済的余裕の確保
日々の業務を意味あるものに変える工夫
どんな業務も捉え方次第で価値を見出せることがあります:
- 意味づけの再構築:
- 単調な業務も「誰かの安全を守っている」と捉え直す
- 1日1つでも「人の役に立った」瞬間を意識的に記録する
- 小さな改善の積み重ね:
- 業務プロセスの効率化提案
- 職場環境の小さな改善
- 自己成長の視点:
- 日々の業務で1つでも新しい知識を得る
- 失敗を学びの機会として捉える
よくある質問(FAQ)
Q1: やりたいことがないまま薬剤師を続けるのは虚無感につながりませんか?
A1: 「やりたいこと」がなくても満足できる働き方は十分に可能です。むしろ「やりたいこと」に固執すると、見つからない焦りから虚無感が生まれることも。薬剤師業務の中で小さな達成感や貢献感を積み重ねることで、徐々に自分なりの意義を見出していくことが大切です。キャリアカウンセリングの調査では、多くの人が「後から意義を見出す」プロセスを経験しています。
Q2: 薬剤師として「やりがい搾取」に陥らないためにはどうすればいいですか?
A2: 「やりがい」と「適正な待遇」はトレードオフではありません。具体的には、①労働環境と報酬のバランスを客観的に評価する、②業界の相場を知る、③自分の市場価値を正確に把握する、④「患者のため」という言葉で無理な労働を正当化されないよう注意する、⑤定期的に自分の働き方を見直す機会を設けることが重要です。
Q3: 薬剤師をやめて全く違う職種に転職するべきでしょうか?
A3: これは個人の状況によります。まず考えるべきは「薬剤師という職業」と「現在の職場環境」のどちらに問題があるかです。職場環境の問題なら転職、職業そのものへの違和感なら職種転換を検討する価値があります。ただし、6年間の教育と国家資格という資産は大きいため、薬剤師のスキルを活かせる関連分野(製薬企業のMR、開発職、医療ITなど)への転換も選択肢として考慮すると良いでしょう。
Q4: 薬剤師として「自分らしさ」を見つける方法はありますか?
A4: 自分らしさは「発見」するものというより、日々の選択で「創造」していくものです。具体的なアプローチとして、①自分が反応する患者層や疾患を観察する、②チーム内での自然な役割に注目する、③エネルギーが湧く瞬間を記録する、④職場以外の活動から価値観を再確認する、⑤小さな選択(服装、言葉遣い、仕事の進め方など)で自分らしさを表現してみる、などがあります。
Q5: 同期や同僚は皆「やりたいこと」を持っているように見えて焦ります。どう対処すればいいですか?
A5: 多くの場合、他人の「やりたいこと」の確信度は外から見えるより低いものです。2023年のある調査では、「明確なキャリアビジョンがある」と答えた社会人は全体の27%に過ぎませんでした。また、「やりたいこと」を語る人の中には、社会的期待に応えるために作られたストーリーを語っている場合もあります。他人と比較するよりも、自分の価値観に正直に向き合い、小さな満足を積み重ねていく方が長期的な幸福につながります。
初めての転職でも安心の No.1 実績
非公開求人の紹介・面接同行も完全無料。
まずは希望条件だけ伝えてみませんか?
- 初めての転職に選ばれるNo.1
- 20代・30代に強い薬剤師転職サイトNo.1
- ハイクラス転職に強い薬剤師転職サイトNo.1
※日本マーケティングリサーチ機構調べ(2021年11月)
\無料キャリア相談を予約/◉ 今すぐファルマスタッフに登録
まとめ:「やりたいこと」神話から解放され、自分らしく薬剤師を続ける

「やりたいこと」がなくても薬剤師として働き続けることは、決して間違いではありません。むしろ、多くの人にとって自然な状態と言えるでしょう。この記事の要点をまとめます:
- 「やりたいこと」神話からの脱却
- 人口の85〜90%はbeing型(状態重視)
- 明確な「やりたいこと」がないのは普通のこと
- being型の人が満足して働くための鍵
- 「仕事でつく嘘」を最小化すること
- 自分の価値観と一致した環境を選ぶこと
- 薬剤師として働く価値の再確認
- 社会的意義
- 実利的メリット
- 仕事とプライベートの分離という選択肢
- 「続けられること」を見つけるアプローチ
- 小さな「好き」の発見
- 「嫌い」の軽減
- 後から発見される情熱
- 自分を守りながら働く実践的戦略
- 市場価値を高める
- 「NO」が言える環境を選ぶ
- 日々の業務に意味を見出す工夫
私自身、薬剤師として15年のキャリアの中で「本当にやりたいこと」を探し続けました。しかし今振り返ると、探すことに執着するよりも、自分の価値観に正直に生き、小さな満足を積み重ねてきた期間の方が充実していたことに気づきます。
結局、大事なのは「やりたいこと」を探すことじゃなくて、「自分に嘘をつかない」ことなんだよ。自分の価値観を大切にしながら、日々の小さな満足を積み重ねていくこと。

クロ

シロ
なるほど!「やりたいこと」がなくても全然OKなんだね。むしろ、無理に見つけようとするより、今の仕事の中で「嫌いじゃないこと」を増やしていく方が、自然な感じがするよ!
「本当にやりたいこと」が見つからなくても、あなたは十分価値ある薬剤師です。「やりたいこと」の発見よりも、自分の価値観に正直に働ける環境を選び、市場価値を高めていくことに集中してみてはいかがでしょうか。それが結果的に、あなたらしいキャリアと充実感につながるはずです。