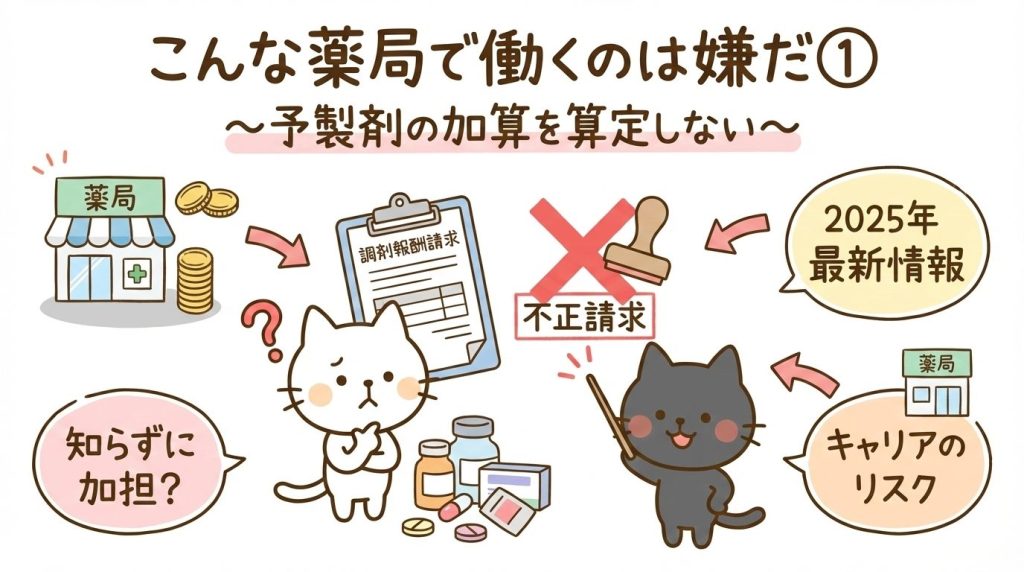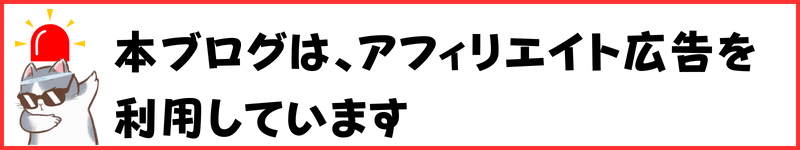薬剤師として働く上で見過ごせないのが調剤報酬の不正請求問題です。特に予製剤の加算算定に関する不正は、知らないうちに加担してしまう危険性があります。2025年現在の最新情報をもとに、正しい理解と対処法について解説します。
目次
はじめに:不正請求のある薬局で働くリスク

薬剤師として働いていく中で、「こんな薬局では働きたくない」と感じる環境はいくつかあります。特に深刻なのが、調剤報酬の不正請求が行われている薬局です。
私も10年以上薬局勤務を経験してきた中で、意図せず不正請求に加担してしまうリスクがあることを実感してきました。今回は特に「予製剤の加算を適切に算定しない」という問題について、2025年の最新制度を踏まえて解説します。

シロ
ねえクロ、こんな薬局で働いていたら要注意とかあったりする?
う~ん、沢山あるからシリーズにして紹介していくね。まずは不正請求している薬局で働いていることだね。

クロ

シロ
不正請求?それって悪いことじゃ…
そう、悪いことだよ。でもコンプライアンスがしっかりしていない職場だと「周りもやっているから」と問題として認識していないケースもあるんだ。

クロ
今の働き方、60秒で診断しませんか?
調剤・病院・企業など 5万件超 の薬剤師求人を保有。
希望条件を入力するだけで、あなたに合う求人を提案します。
- 最短60秒で完了する簡単登録
- 条件にマッチした厳選求人をご紹介
- 非公開求人も多数保有
◉ 最適な求人をチェックする
予製剤の加算を適切に算定しない問題とは

2025年最新:計量混合調剤加算の点数と規定
2024年度の調剤報酬改定で計量混合調剤加算の点数は下表の通りとなっています。この点数は2025年も継続されています。
| 剤形 | 通常点数 | 予製剤の場合(100分の20) |
|---|---|---|
| 液剤 | 35点 | 7点 |
| 散剤・顆粒剤 | 45点 | 9点 |
| 軟膏剤・硬膏剤 | 80点 | 16点 |
予製剤とは、あらかじめ想定される調剤のために複数回分を製剤し、処方箋受付時にその製剤を投与することをいいます。例えば、処方頻度の高い小児科や皮膚科などでは、よく出る処方を事前に調剤しておくことがあります。
よくある事例として、予製加算を算定しなければいけないところを、通常のまま加算を算定しているケースだね。

クロ

シロ
予製加算?クロ、ごめん。全然何を言っているか分からない…
それじゃあ簡単に説明するね。粉薬を二種類MIXしたり、軟膏剤を二種類MIXしたりする際には計量混合調剤加算というのがプラスされるんだ。簡単にいうなら、お薬を用意するのが手間だからプラスでお金を払うねってことなんだけど、この点数は予製剤の場合は8割減になるんだ。

クロ
不正請求の実態と問題点
予製剤の加算を算定しない不正請求は、次のようなケースで発生します:
- 処方頻度が高く、事前に調剤(予製剤)しているにもかかわらず、通常の計量混合調剤加算を算定
- 医療機関の処方せんの内容を事前に把握し、予め調剤しておきながら予製剤とみなさず通常加算を算定
- 予製剤であることを認識しながらも、「薬局の経営が厳しい」などの理由で意図的に8割減の算定をしない
この問題の深刻さは、1件あたりの不正金額は小さくても、長期間にわたり多くの処方箋で行われると、結果的に大きな不正請求額となる点です。
クロ:
- 液剤:35点→7点
- 散剤等:45点→9点
- 軟膏剤:80点→16点

シロ
こんなに下がってしまうなら、確かに約束処方が多い小児科や耳鼻科、皮膚科の処方を多く受ける薬局ではやっている薬局はあるかもしれないね。
やらなきゃ経営できないからという理由でやってしまってた薬局も昔はあったようだけど、今はもうそういう時代ではないからね。

クロ
2025年の法規制・監査体制の強化

2025年現在、調剤報酬の不正請求に対する監視体制は一層強化されています。厚生労働省は2024年度の調剤報酬改定に合わせて監査体制を見直し、特に次の点を強化しました:
- 処方せんと調剤録の照合強化:電子処方せんの普及に伴い、調剤日時と処方せん受付日時の整合性チェックが自動化
- 予製剤の適正な算定の徹底:特に頻度の高い処方に対する予製剤の取り扱いについて、明確化された通知の発出
- 不正請求に対する罰則の強化:健康保険法に基づく行政処分の公表範囲拡大、取消処分相当の自主廃業も公表対象に
近年発覚した不正請求事例では、指定取消になった薬局に加えて、不正が発覚する前に辞退・廃業した薬局についても公表されるようになりました。
不正請求が発覚した場合の処分
調剤報酬の不正請求が発覚した場合、以下のような処分が行われます:
- 経済的制裁:不正請求額の返還(通常5年間分さかのぼって調査)
- 行政処分:保険薬局の指定取消、一定期間の再指定禁止
- 行政処分の公表:薬局名、開設者名、不正内容、不正請求金額などを公表
- 社会的信用の失墜:地域からの信頼喪失、関連グループ全体への波及
薬局の経営に大きな打撃を与えるだけでなく、そこで働く薬剤師にとっても、キャリアやメンタル面での影響は計り知れません。知らなかったでは済まされないケースもあるのです。
ファルマスタッフで転職相談満足度 96.5%
就業先を直接訪問したコンサルタントが残業・雰囲気まで共有。
東証プライム上場グループ運営で安心です。
- 現場を知り尽くしたプロによるサポート
- 書類では分からない職場の空気感も把握
- 24時間いつでも相談可能なシステム
◉ ファルマスタッフに登録する
薬剤師として取るべき対応:問題発見から解決まで

現状の確認方法
もし、自分の勤務先の薬局で予製剤の加算が適切に算定されているか確認したい場合は、次のステップで確認することができます:
- 調剤録の確認:予製剤とされているものが適切に記録されているか
- レセプト請求の確認:予製剤が「100分の20」の点数で算定されているか
- 薬局内の業務手順の確認:予製剤の取り扱いについて明文化されたルールがあるか
患者の待ち時間も減るので、8割減にするのはどうかとも思うけど、予製剤でお渡ししているのに、減算しないのは、コンプライアンス違反。もし、心当たりがありましたら…

クロ

シロ
もし、自分の働いている薬局であったらどうしたらいいのかな?
問題発見時の適切な対応
もし予製剤の算定に問題があると気づいた場合、次のように対応することをお勧めします:
- 管理薬剤師への確認:まずは管理薬剤師や上司に確認する。その際、非難するのではなく、「なぜその算定方法なのか教えてほしい」というスタンスで尋ねる。
- 説明が不十分な場合:管理薬剤師の回答に納得できない場合は、調剤報酬点数表や留意事項通知などの根拠資料を示しながら再確認する。
- 組織的な問題の場合:管理薬剤師も認識していたり、本社の方針などの組織的な問題である場合は、状況を記録しておく。
その際、「これって悪いことですよね?」というスタンスで聞いてしまうと険悪なムードになるので、注意しようね。

クロ

シロ
もし、聞いてみたら、さっきクロが言ってたように「やらなきゃ経営できない」とか言われたら、どうしたらいいかな?
その時はケースバイケースになるかな。管理薬剤師の独断なのか組織ぐるみなのかにも変わってくるし、そして「そんなところからは逃げ出せ」と口で言うのは簡単だけど、実際、薬剤師の転職事情も変わりつつあって、簡単に転職できなくなっているからね。

クロ
内部告発・通報の選択肢と保護制度
明らかな不正請求が続き、内部での改善が見込めない場合は、「公益通報者保護法」に基づく内部告発や行政通報の選択肢もあります。2022年の法改正により通報者保護が強化され、2025年現在ではより安全に通報できる環境が整いつつあります。
ただし、通報には慎重な判断が必要です:
- 通報前に証拠や記録を適切に保存しておく
- 可能であれば、専門家(弁護士等)に相談する
- 通報先や方法を慎重に検討する(内部窓口→行政機関→報道機関の順が基本)

シロ
でも悪いことだってわかった上で働き続けるのもつらいよね…
そうだよね、自分に嘘をついていると、自分のコト嫌いになるからね…本当に板挟み状態。とりあえず、逃げ出そうと思えば逃げ出せる余裕を持っておくことが必要だと思う。

クロ
よくある質問(FAQ)
予製剤は具体的にどういう場合に該当しますか?
予製剤は「あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与すること」と定義されています。例えば、小児科クリニックや皮膚科クリニックの処方でよく使われる混合散剤や混合軟膏を、患者さんの来局前に事前準備しておく場合が典型例です。患者さんの待ち時間短縮のための工夫ではありますが、調剤報酬上は適切に減算する必要があります。
予製剤と判断される明確な基準はありますか?
処方箋受付前から複数回分の混合調剤を行っていた場合は予製剤と判断されます。具体的な証拠としては、調剤録の記載時刻や監視カメラの映像、従業員の証言などが用いられることがあります。また、調剤業務手順書等に「頻度の高い処方は事前に準備しておく」などの記載があれば、予製剤と判断される可能性が高まります。
不正請求に気づいても黙っていた場合、責任を問われますか?
薬剤師個人としての法的責任は状況によりますが、不正請求の事実を知りながら長期間黙認していた場合、共犯と見なされるリスクがあります。また、薬剤師法で定める「薬剤師としての倫理」の観点からも問題があるとされる可能性があります。新入職員など立場が弱い場合でも、最低限自分の関わった業務については記録を残しておくことが重要です。
調剤報酬の規定はどのように確認できますか?
最新の調剤報酬点数表や留意事項通知は、厚生労働省のホームページで確認できます。また、日本薬剤師会や各都道府県の薬剤師会でも情報提供や解説資料を発行しています。不明点がある場合は、地方厚生局の担当部署に問い合わせることも可能です。日頃から最新情報をチェックし、制度への理解を深めておくことが大切です。
初めての転職でも安心の No.1 実績
非公開求人の紹介・面接同行も完全無料。
まずは希望条件だけ伝えてみませんか?
- 初めての転職に選ばれるNo.1
- 20代・30代に強い薬剤師転職サイトNo.1
- ハイクラス転職に強い薬剤師転職サイトNo.1
※日本マーケティングリサーチ機構調べ(2021年11月)
\無料キャリア相談を予約/◉ 今すぐファルマスタッフに登録
まとめ:適切な薬局選びとプロフェッショナルとしての姿勢

予製剤の加算を適切に算定しない問題は、薬剤師として働く上で見過ごせない重要な問題です。特に次の点を心掛けましょう:
- 事前確認の徹底:就職・転職時には、薬局の調剤報酬算定の考え方について確認する
- 継続的な学習:調剤報酬の最新動向や正しい算定方法について学び続ける
- 問題への適切な対応:不正請求に気づいた場合は、冷静かつ適切に対応する
- 逃げ道を確保:いつでも転職できる準備を日頃から整えておく
予製剤の加算を算定していない薬局で勤務していたら…

クロ
- まずは管理薬剤師や上司に、何故、予製剤の加算をとっていないのか聞いてみる。
- 聞くことが出来ない、もしくは分かった上でやっていないのであれば、いつでも逃げ出せる余裕をもつこと(辞めても大丈夫なように次の職場のあたりをつけておく等)

シロ
うん、でも実際辞めるかどうかは慎重に考えた方がいいよね。
そうだね。自分に嘘をついて働き続けるのはやめましょう、心が死にますからね。

クロ
薬剤師としてのキャリアは長いものです。短期的な利益や便宜のために、長期的な信頼やキャリアを損なうことがないよう、常に誠実さとプロフェッショナリズムを持って業務に取り組むことが大切です。
予製剤の加算を正しく算定する薬局で働くことは、単なるコンプライアンスの問題だけでなく、自分自身の薬剤師としての価値観や誇りにも関わる重要な選択なのです。